
こんにちはうにこままです!
皆さんはお子さんがお絵描きをしてる時や、見せに来た時、何て声をかけてますでしょうか?
私は「上手だね~」「何描いたの?」という言葉を頻繁に使っていました。
普通に言っている方も多いのではないでしょうか?
でも実はこの言葉、使ってはいけないNGワードだったのです!
今回はそのような言葉を使わない子供の絵の褒め方、絵に関してのおすすめの本や道具をご紹介したいと思います。

・子供の絵を何て褒めたらいいのか知りたい
・もっとお絵描きを好きになってもらいたい
・おすすめの本や道具はないかな?
このような思いをお持ちの方に、私は1冊の本を購入して常識を覆され、子供とのお絵描きに自信を持って接する事が出来たので、是非読んで頂けたら嬉しいです!
目次
常識を覆されたおすすめの本
最近2歳のうにこに学習机もどきを購入してから、うにこがお絵描きをする時間がすごく増えました。
私はいつもうにこが何を書いても「上手だね!」と褒めちぎり、そして早くお絵描きが上手になって欲しい思いもあって「これ何描いたの?」と頻繁に言っていました。
さらに私はもっとお絵描きが上手になって、知育的にも良くなるような関わり方はあるのかな?と気になり、子供の絵のことに関する1冊の本を読んでみました。
読んでみると最初から私の常識を覆す内容でした。
「上手だね」という言葉は無意識に評価している!?
子供が自由にお絵描きをした時、そこには上手も下手もないんだそうです。
私達大人が言う「上手」は、言った本人の価値観から出た言葉です。
大人は具体物を本物そっくりに描いたものを上手に描けていると認識するそうですよ。

確かにぐちゃぐちゃに描かれたものよりも、少しでも顔に似たように描けた時の方が上手!と思ってるな・・・
その勝手な大人の評価が、子供に「絵は上手に描かなくちゃいけないのか」と思わせてしまうそうです。
それが子供の自由な発想を奪うことになる。
なるほどな~!と目からウロコでした!
本当に絵を描くことが好きな人は、他人からの評価が気にならない人かもしれません。
そしてそのような大人になれるのは、子供の時に大人から評価されず、自分の好きなように描いてきたからかもしれません。

絵だけじゃなくて他の事全般に言えることでもありますよね。

自分の好きでやってる事って、他の人の評価なんか気にならないですもんね
「これは何?」「何描いてるの?」と聞くと大人の求めるものしか描けなくなる!?
これも「上手だね」と言ってしまう事の弊害と似ているのですが、小さい子が描く絵は具体的な何かではない場合が多いそうです。
使いたい色で手を動かしたらこんな風になる事を楽しんでいるだけ。

確かに何か描くというより、いつもなぐり書きだな・・・
そんな楽しんでいる時に「これは何?」と聞くと、「何か具体的な物を描かなくちゃいけないの?」と思わせてしまうようです。
上記のように、大人は具体物を本物そっくりに描いたものを上手に描けていると認識するので、これもまた具体的を描かなくてはいけないという勝手な価値観からくる言葉です。
そのような言葉を言い続けていると、大人が求める何か具体的なものしか描かなくなってくるそうですよ。

そしてそれは心からお絵描きを好きになれるはずありません。
本当に大人は価値観に縛られてるなぁと感じますよね。
NGワードを使わない上手な褒め方
「上手だね」「これは何?」を言ってはいけなかったら、子供がお絵描きした時何て言えばいいの?と思いますよね。
可愛い我が子が一生懸命になって描いた絵は褒めてあげたいものです。
そこでお子さんがお絵描きしている時や見せに来た時は、その絵を認めてあげて大人の感じた事を言ってあげるといいそうです。
紹介している本にはこのような言葉が例として載っていました。
①具体的なものを描いていないけど赤色が目立つ絵→この赤色が綺麗!ハッとするね。
②子供が絵を見せに来て、「ここをこうしてみた!」と言ったら→「そうなんだ、ここをこうしてみたんだね」
①は大人が感じた事を、②はリピートしているだけですが、話を聞いてるという事が伝わり、相手を認めている事に繋がるんだそうです。
他にも「描くのが好きなのね」と、事実を言うだけでもいいようですよ。
この本では相手を認めるという事が褒める事というふうに紹介されています。

これだったら難しく考える事なく子供に伝えられそう!
ただ、ちょっとこの本で腑に落ちない所があって、「これ何描いてるの?」という言葉を使ってはいけない理由は分かったんですが、純粋に何を描いてるか聞きたい気持ちもあるんです・・・
具体的である必要はない事は承知で、子供が楽しそうに描いていたら、もしかしたら何か楽しい事思いついて描いたのかな!?とか、今は何に興味を持ってるんだろう?とか・・・

これについては著者の井岡由美さんの書かれた所では納得いくものがありませんでした。
ただ、あとがきで本の監修者である高濱正伸さんのページにこう書かれていました。

何となくこの文章を読んでほっとしました・・・
自分が勝手に求める具体的な何かを描いて欲しい為に「何これ?」と聞くのではなく、自分も子供の気持ちに戻ったような好奇心で聞く。
聞く内容は同じでも大人の気持ちがこのように違うと、子供に与える影響が違ってくると、私は解釈しています。
本を読んだ感想
今までの常識を覆されてびっくりしましたが、自分が今までいかに自分の価値観を子供にぶつけていたか、この本を読んでよく分かりました。
これは絵だけに限らず工作も勿論そうですし、日常生活のあらゆる場面でも当てはまるなぁと思いました。
子供は自分の思い通りになる存在なのではなく、ただ小さくて1人で出来ないことも多いけど一個人ですもんね。

ある程度は見守り、自由にさせてあげるのが大事だなぁと感じさせてくれる本でした。
そして子供の心と頭を同時に伸ばしてあげられるかは、周りにいる大人の対応がカギを握っている重要さも伝えてくれる本でした。
今回はここで紹介した事以外にも、絵に関することを通して、将来子供が社会に通用する大人になる為に大切な事がたくさん書かれていますので、子供をお持ちの方には是非おすすめします!
私は著者の井岡由美さんがアート×教育をテーマに開催している創作ワークショップ「Atelier for KIDs」があるようで、そこに是非に通わせてみたいなぁと思ったんですが、高知県の小学校や保育所で行っているようですね。

でもお家でも出来るような創作を、ポイントを踏まえて紹介して下さっているのでそこも為になりましたよ!
幼児におすすめのクレヨンと色鉛筆
ここで、子供のお絵かきに対する大人の対応がどのように大事か理解し、もっとお絵かきをさせてあげたいなと思われた方に幼児におすすめのクレヨンと色鉛筆をご紹介します!
まずはまだ小さいお子様で、お絵かきをし始めた子にはこちらのクレヨンがおすすめです。
これは形が三角のクレヨンになっていて幼児が握りやすいように少し太めのクレヨンになっています。
三角になっている事できちんとした持ち方をサポートしてくれるようで、素材も指につきにくくなっていますよ。

私は幼児教室でこれをおすすめされたので、1歳の頃から2歳の現在もずっとこれを使っていて本人も使いやすそうですよ!
少し手先が器用になってきたなと思ったら、同じく三角の形の色鉛筆がおすすめです。
私は最初100均で買った色鉛筆を使わせてあげたのですが、まあ色が出ないこと・・・
幼児は筆圧が弱いので100均では力不足で買い直しました。
くもんの三角の色鉛筆はすごく筆圧がなくてもすごくはっきり色が出て本人もそればっかり使っています。
ただこの色鉛筆、色が6色しかないんですよね・・・
私はまあいっかと思って6色のものを購入したのですが、もっと色が欲しい方は同じく三角の色鉛筆のしまじろうタイプが12色入っています。
ちょっと高い気もしますが、レビューも好評価ですし色鉛筆を入れる筒がついているのがいいですよね。

しまじろうタイプの方が色鉛筆の長さが長いのでその分と考えればそんなに高くないかも!?
これらの三角の色鉛筆は普通の鉛筆削りは使えないので、専用の鉛筆削りを同時に購入される事をおすすめします!
これは三角も丸い普通のタイプも両方削れるので1個持っておけば便利ですね。
そしてしまじろうといえば通信教育のこどもちゃれんじですね。
私も娘もこどもちゃれんじが大好きでずっと習っています。
こどもちゃれんじについては「こどもちゃれんじぷち・ぽけっとの口コミ!初めての子育てや忙しいママにぴったりな理由は?」で口コミしてますので、良かったら読んでみて下さい。
まとめ
私が子供の絵の事に関して衝撃を受けた内容をお伝え致しました。
結構普通に使っていて、まさかそれが良くないかも?なんて思いもしない事ですよね。
保育士さん達でさえ子供にそのような対応をしている方も多いような気がします。
私はこの本を読んで、子供がどう育っていくかはいかに大人のなにげない言葉も影響されるんだなぁと身が引き締まり、どうすればいいのか学ばせて頂きましたよ。
そして私の記事も少しでも読んで頂けた方のお役に立てれば幸いです!
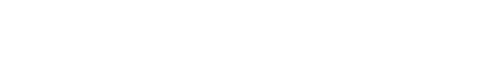





コメント
[…] […]